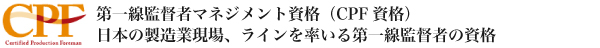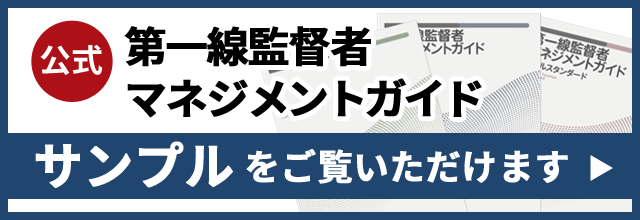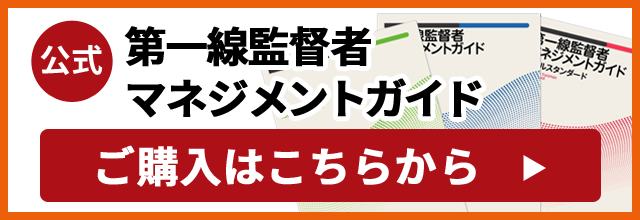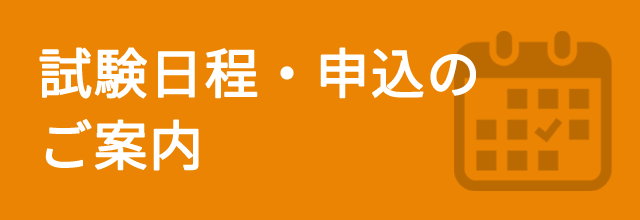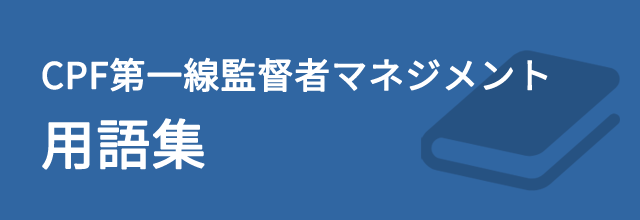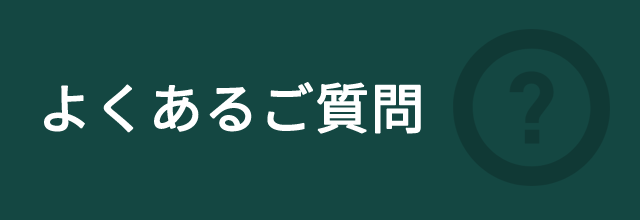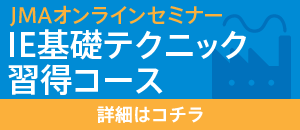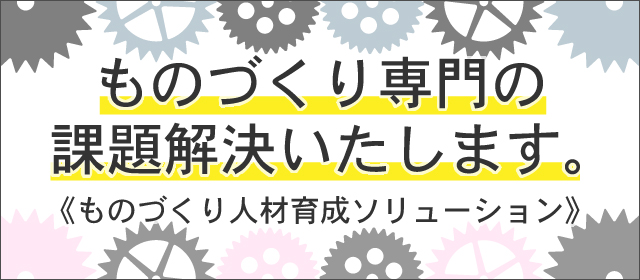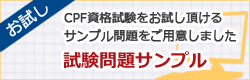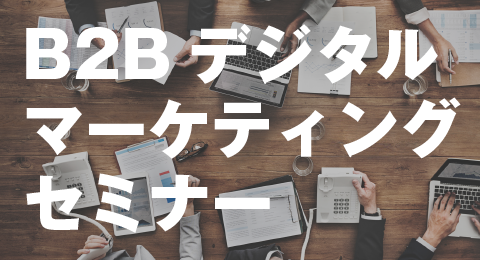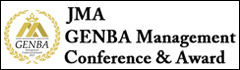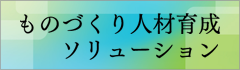能率協会の資格制度の活用目的とは? CPF合格者インタビュー②vol.2
CPFホルダーの
東京電力ホールディングス株式会社
経営企画ユニット グループ事業管理室 調達管理グループ 能力開発担当課長
谷口 正洋 様
に事務局の勝田がインタビューをしました。(以下敬称略、お役職はインタビュー当時)
能率協会の資格制度の活用目的とは?
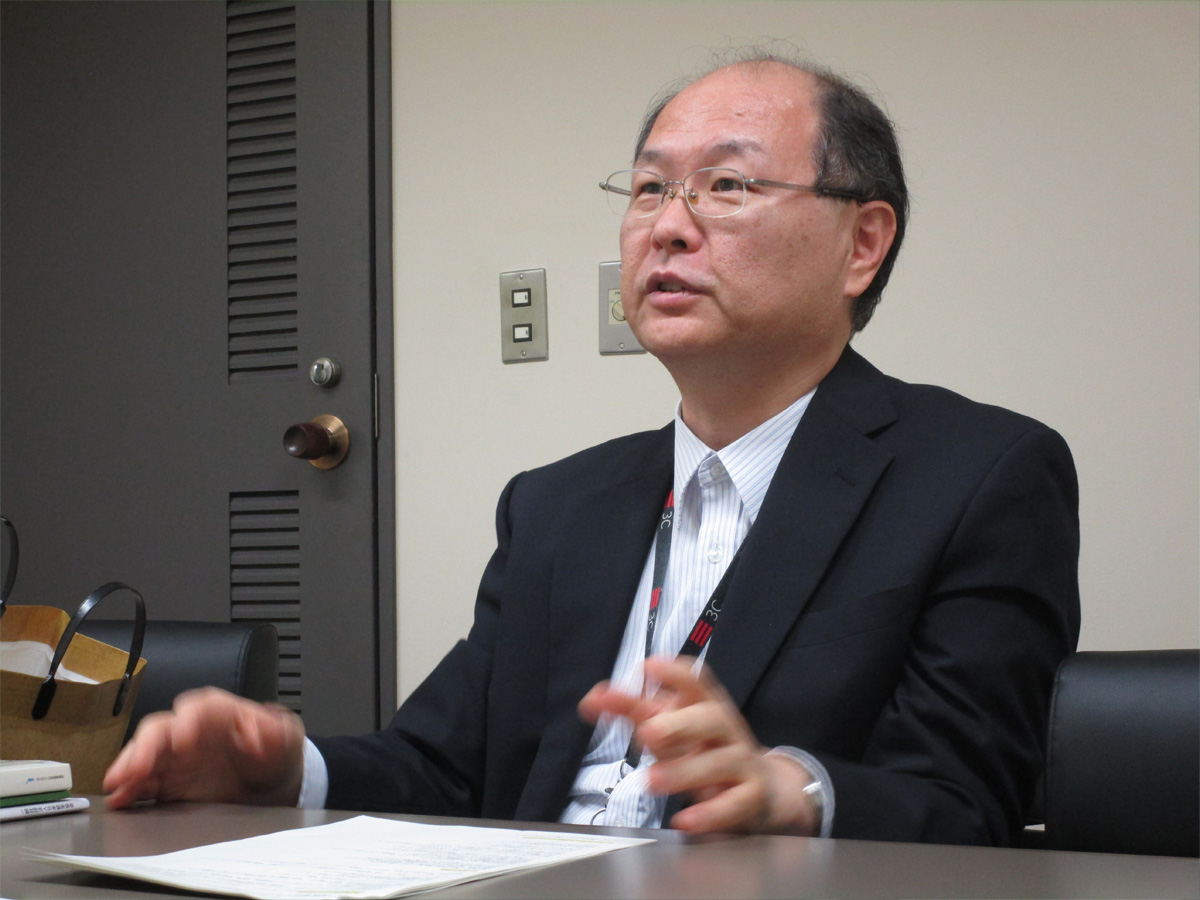 勝田
勝田
CPFの話の前に、組織的に導入されたCPPについて触れさせていただきます。
谷口さんは調達組織の中で教育担当をなさっているわけですが、日本能率協会の資格制度のCPPを組織的に導入いただいております。
導入するきっかけはどこにありましたか。
その経緯について少し教えていただきたいと思います。
谷口
調達を業務レベルで最低限のところからいいますと、手配購買から始まります。
取引先にこういったものを頼むという手配をかけるものです。
コストダウンを進めることになれば、取引先同士で競争してもらい、その競争の中で値段を下げてもらう競争購買へレベルアップします。
私どもは今、競争購買レベルのステージにいて、競争率が60%ぐらいでしょうか。
ただ、調達品の中には競争できる分野とそうでない分野が存在します。
そこで、次の段階に進んで戦略的な購買レベルに入っていかなければならないと考えているのです。
しかし、職員全体で見ると、そこまでの知識レベルに達していないことを自覚しています。
それで、メーカーさんなど先に進んでいる企業のノウハウをどんどん吸収してそのレベルにのぼっていこうと計画しました。
職員の一部は既にそのレベルに達していますが、全体のレベルを上げるためには何か教科書のようなものが必要になってきます。
そこで見つけてきたのが日本能率協会のCPPという調達プロフェッショナルの検定でした。
組織全体を底上げするのにもってこいだと考えたわけです。
私どもも以前から社内でテキストを作って研修を進めてきました。
しかし、社外に通用するものにしないといけませんし、時代の流れに合わせた変化にも対応する必要があります。
日本能率協会なら時代が変わればテキストを改訂していただけると聞きました。
それで、CPPという検定を使うようになり、これまでの3年間で250人がひと通り受験し終わった状態です。
研修の事務局としてはCPPの基礎の上にいろいろな戦略に基づいて知識を高め、コストダウンを進めていきたいと考えています。
勝田
CPPの導入を通じ、調達に関する基礎的な考え方、スキルを学ぼうということですね。
谷口
そうです、そういう形になります。
CPPを勉強したうえで不足している知識を、さらに積み上げようと考えています。CPFもその候補の一つです。
つづく 2/14